川内JCとは

社会への奉仕
友情
個人の修練
年間スローガン
基本理念
親切心を持って誰もが輝き 希望溢れる未来へ
基本方針
- 丁寧な会議と時代に即した手法による魅力発信
- 品格ある経済人としての高潔な人間力向上
- 自立心と判断力を醸成する青少年の育成
- 地域行事への参画による郷土愛の醸成
- 創立 55 周年記念事業による謝意の表明と未来への一歩
理事長所信(あいさつ)
はじめに
あなたは今、情熱を持ち精一杯取り組んでいるものはありますか。
私には JC があります。JC は自分の意志で入会を決意し、多くの仲間たちと出会い、楽しいことも辛いことも、大好きな仲間たちと共に情熱を持って精一杯取り組んでいます。私はそれを苦労だと感じたことはなく、「まちのため」「みんなのため」「じぶんのため」に私にできる最大限の努力をしています。
2014 年に日本柔道連盟が掲げた「柔道 MIND」の中に、礼節(マナー)、自立(インディペンデンス)、高潔(ノビリテ ィー)、品格(ディグニティ―)の4つの柱を基に人間形成を行う指針があります。創始者である加納治五郎先生の教えを基本とする柔道家については必要な心であり、その中でも、美しい倫理観を持ち、行動や言動が落ち着いて心 が美しい状態を品格があると言います。さらに、後ろめたいことをせず、誠意のある生き方をすることで周囲の信頼に溢れ、社会の中で健全な絆を育むことができる高潔な人とは、柔道家だけでなく青年会議所メンバーである上で必要 な人格であり、そのような品格のある高潔な人でありたいと常に心掛けています。
しかし、そのような人でも一人の灯は小さなものです。一人でできることには限界があり、品格ある高潔な人であってもその微力さに心痛くなることがあります。しかし、その小さな灯も、大好きな仲間たちと情熱をもって社会課題に向き合い、その想いを集結させることで大きな灯となり、まちの未来を切り拓いていけると私は信じています。
変化の絶えない時代に私たちに託されていること
世界は特定の地域での対立が軍事的緊張を高めており、国際社会における様々な問題が加速することが懸念されています。その中でも、私たちの暮らしに直結する物価上昇や異常気象による災害の甚大化、貧困問題など多くの問題を抱えています。
しかし、人工知能の進歩や再生可能エネルギーの拡大、地方創生への取組みなど課題解決のための対策も多様性を増し、解決に向けた努力をやめることなく私たちは歩み続けています。
日本に目を向けてみると、人口減少や少子高齢化が深刻化し、2026 年にはすべての団塊の世代が後期高齢者と なります。人口減少に歯止めをかけることは日本の大きな課題として取り組むべき難題ですが、若い世代への雇用環 境改善や生活しやすい環境作りなど地方へ人の流れをつくることが優先されています。しかし、医療技術の進歩により高齢者の健康寿命が延伸しており、日本は世界一の長寿国家となりましたが、その一方で、医療・介護需要の増大が見込まれ扶助費増加による若者への負担が増加しているのも事実です。
さらに商工業、農林漁業などの担い手不足問題は深刻化しており、事業継承ができず廃業をやむなく選択する企 業や労働人口の減少による産業の不安定化にも大きな要因を与えています。その中で、我々川内青年会議所は 54 年もの間、薩摩川内市及びさつま町の発展に尽力してまいりました。これは、大きな視野で社会課題の解決に取り組み、様々な問題に尽力してきた多くの先輩方をはじめ、川内青年会議所 の理念に共感いただいた多くの皆様の努力の賜物であります。だからこそ、青年経済人としてこのまちに住み暮らす私たちは、これから先の未来を見据え、これからの未来を託す 子どもたちへ、今、まちづくりへの情熱を背中で魅せる必要があります。目の前のことを最大限の努力で、汗をかき、走りきることが、昔から変わらないこのまちを牽引してきた先輩方の姿であり、追いかけるべき姿だと思います。そして、そのバトンをしっかりと受け継ぎ、その想いを未来ある子どもたちへ継承することで、私たちの意思は後世へ波及していくものだと信じて、社会課題の解決を行っていきます。
Story 委員会(総務広報委員会)
青年会議所では様々な会議が行われ、メンバーが集い情報交換を行います。時代の流れと共に様々な手法で行われる会議の中で最も基本的な部分を繰り返し行う中で、我々の事業はより良いものに進化し、まちの発展に尽力してまいりました。会議の進行を円滑に行うことや、設えを整えることで質の良い会議が実施され、丁寧な会議を意識することがメンバーの成長に直結すると考えます。
総務の分野では、各種会議を丁寧に円滑に実施するために活動し、今一度、青年会議所としての在り方を確立します。会議の質を高めることにより、素晴らしい事業の構築が行われ、川内青年会議所がこのまちに信頼され選ばれる存在になる機会とします。
広報の分野では、川内青年会議所の素晴らしい部分や伝えたいことなどを分かりやすく広報するためにストーリー性を持った広報活動を実施します。またその中で、PRの手法やどこの層をターゲットにすればより良い広報が行われるかなど、今の時代に即した広報を実施します。川内青年会議所の積極的な広報にスピード感をもって尽力することで、メンバー自身が川内青年会議所の魅力を再確認し、広く川内青年会議所の魅力を発信していきます。
Gentle Upgrade 委員会(ひとづくり委員会)
(ひとづくり事業)
私は青年会議所の先輩から「リーダーは次のリーダーを育てる役割を担っている」と教えていただいたことがあります。「ひと」を「つくる」というとても難しい言葉に私なりの答えを出せないでいた時に、先輩の言葉はすごく感銘をうけました。
このまちを牽引するリーダー像は様々ですが、その根幹にあたる部分についてはすべて「ひと」であり、ある一定のレベルまではリーダーとしてだけではなく、社会人としてスキルアップする(「つくる」)べきであります。また、川内青年 会議所においては近年の急激なメンバー拡大に伴いその半数以上がアカデミーメンバーでありメンバーの経験値や人間力の向上まで人材育成が追い付いていないことが現状です。経験値については積極的に様々な事業に参加することで向上していきますが時間がかかります。しかし、人間力の向上については、今だから取組むべき課題であり私を含むJCメンバーすべてに言えることだと考えます。誰もが次のリーダーとなれるよう、人間力やスキルの向上をすることが今の川内青年会議所に必要不可欠で、その結果多くのリーダーが排出できる組織となり、青年会議所活動だけでなく様々な場所でメンバーが活躍することでまちの発展に寄与します。
(会員拡大)
40歳までと決められた組織の中で入会と卒会を繰り返し、メンバーが入れ替わることが至極当然です。 2026年も4名の卒会者を予定しており、確実にメンバーが減少します。メンバーが減少すると川内青年会議所の力が 減少し、その影響力も減少します。ある一定以上のレベルで事業に取り組むこと、一定以上のレベルでまちの発展に寄与することを実現するためには、メンバーを拡大しメンバー数を一定以上に保つことが重要視されます。また、同じ志を持つ友人が多いほど我々の使命である「明るい豊かな社会の実現」に近くなることは当然です。年齢制限のあるこの団体が常にまちの若者で構成されることで、このまちにフレッシュさをもたらし、地域に根付いた団体であり続けるために会員拡大は重要です。まだ見ぬ同士が一人でも多く入会し、川内青年会議所を通した結束の和が広がるために会員拡大も全力で取り組みます。
みらい共育委員会(青少年育成委員会)
川内青年会議所が創立以来続けている事業のひとつに、青少年育成事業があります。私自身もその青少年育成事業に参加していた子どもでもあります。私が実際に参加した青少年育成事業を今度は計画し、実施する側で参加するのは感慨深いものがあります。当時と変わらないことは大人が子どもたちのために一生懸命になることです。子どもながらに父のその姿は覚えており、今になると感謝しかありません。そして、私も子育て世代となり実際に小学生を育てる親として1つだけ守って欲しいことがあります。それは自ら考え行動する自主性です。現在、様々な情報が各種 SNSで広がりを見せ、一種の中毒症状のようにSNS への依存傾向が強い若い世代が増えている中、数ある情報の中のどの情報を信じ、どの情報に頼るなどは自身で考えて判断しなければいけないと感じます。青少年育成事業の中で、自身の力で情報を整理し、それを自分の力で考え、判断し解 決する手段を学ぶことが、この情報化社会に生まれた子どもたちに最も必要なスキルであると考えます。そして、その事業を一生懸命行う大人達の姿を未来の宝である子どもたちに魅せることが、我々の想いを伝える最高の手段であると考えます。そうすることで、子どもたちが将来自分の力で生き抜くことができるスキルを習得し、次の世代にバトンを渡す担いを継承してくれると信じます。
祭 Re:builders委員会(まちづくり委員会)
明るい豊かな社会を目指す青年会議所にとって、まちづくりとは一番の根幹にあたる部分です。そこには様々な社 会課題が存在し、そのすべてに対して行動し尽力することは青年会議所にとって重要です。
その中で薩摩川内市及びさつま町にとって大きな課題は、「若者の人口流出」「U ターン希望者の減少」だと感じます。「雇用の拡充」「生活レベル」「都市部へのあこがれ」など様々な要因があり、高校卒業後に進学や就職で地元を離れる青年が多く存在し、そのほとんどが帰ってくることはありません。
では、我々が生まれ育ち、親しみやすいこの地に残りたい、帰ってきたいと思えないのはなぜでしょうか。それは、このまちに残る伝統や歴史を感じることなく大人になるからだと私は感じます。
薩摩川内市やさつま町では古くから伝わるどの町にも負けない大小様々な文化が根強く残っています。そのすべてにおいて、大人たちがその地区に住み暮らす子どもたちのために企画・準備し楽しませてきたものだと思います。
子ども時代からその文化に携わりたくさんの大人とふれあい、大人たちの熱い想いに触れることで、地元の子どもたちに郷土愛が醸成し、この文化を私たちが引き継いでいきたいと感じることが、「若者の人口流出」「Uターン希望者 の減少」に歯止めをかけると信じています。その結果、メンバー自身もこのまちの魅力を再確認することができ、子どもたちが今以上にこのまちを大切に想うことができるようになります。そうすることで、まちに雇用が増え、労働人口減少にも歯止めがかかり、若い世代の活気が薩摩川内市及びさつま町の地域経済活性化に寄与し、私たちの想いはまた次の世代に受け継がれていきます。
55Thanks 委員会(55 周年記念事業実行委員会)
川内青年会議所は今年で創立 55 周年を迎えることができました。そこには多くの先輩方の弛まぬ努力が存在し、その一つひとつが紡がれ今の軌跡があります。その軌跡の中に私たちは生かされており、バトンをしっかり受け止め、次の世代に想いを継承するために駆け抜けなければいけません。
社会情勢や川内青年会議所のおかれる立場など 55年前とは確かに違います。しかし、心の中にある「まちに対する想い」はこの 55年間しっかりと継承され紡いできました。代々受け継がれてきた信念や誇りをしっかりと持ち、日々変化する時代をしっかりと見つめ、時代に即した社会課題の解決への取り組みを実施していかなければなりません。
そのために、今一度川内青年会議所の歴史を振り返り、これから先の未来へバトンを継承するために記念事業を行います。歴史と伝統ある川内青年会議所を築き上げてこられた先輩方への感謝を示す記念式典と、これからの時代に向けた我々の想いを継承するための未来へ繋がる事業を行います。
その中で、今後の川内青年会議所があるべき姿をメンバー全員で認識し、今まで以上の当事者意識が芽生える機会とします。さらに、このまちに川内青年会議所が必要とされる存在であり続け、今まで以上に影響力がある組織に成長する機会とします。
結びに
私は、どんな人にもそこに生まれ落ちた意味があると思っています。多くの選択肢があり、たくさんのチャンスがある中で、たまたま同じ時代に産まれ、それぞれが成長を遂げ、川内青年会議所を選び入会しました。そこで出会った仲間たちは軌跡で紡がれており、その軌跡に私は感動すら覚えます。この仲間たちと育んできた友情が集った時に大きな力となり、その仲間たちがこのまちを想う情熱が行動力になります。その強い想いを継承することが、私たちに託された最大の使命であると思います。 2026 年度は、メンバー同士の友情をさらに深め、JAYCEE として高潔な青年経済人への成長を目指し、成長した我々メンバーが様々な形でまちの発展に寄与することが、薩摩川内市及びさつま町の財産になるようにします。さらには、我々が受け取ったバトンを次の世代に引き継ぐための一年間であると胸に刻み、社会課題の解決に向けて常に挑戦し未来を見据えた活動を楽しみながら展開して参ります。
「 継承 ~青年の情熱がまちの未来を切り拓く~ 」
Story委員会 委員長

東 はつき
青年会議所の運動•活動は、理事会や委員会等の会議により方向性が定まるため、より質の高い会議運営と組織力の向上が求められます。また、市民やアカデミーメンバーへの認知度と関心をさらに高め、青年会議所の魅力や運動•活動への理解を深めるための広報活動も欠かせません。
丁寧な会議運営を実現するために、役割分担と事前準備の徹底により、会議中は議論と意思決定に集中できる体制を整えます。また、動画配信を活用し、事業の背景や想いが伝わるストーリー性を持った広報を展開します。様々なSNSを活用し、ターゲット層に応じた時代に即したPR方法を学び実践することで、リアルタイムで効果的に魅力を発信し、より多くの人に情報を届けます。
会議の質向上と組織力の強化に加え、効果的な広報活動を推進することで、川内青年会議所の魅力と想いへの理解をより一層深めます。そして、組織が一丸となり市民から信頼され、これからも選ばれ続ける存在となります。
Gentle Upgrade委員会 委員長

橋口 眞博
(ひとづくり事業)
川内青年会議所では、現在入会3年未満のアカデミーメンバーが急増しており、経験の蓄積が十分ではないことが懸念されています。そのため、リーダーとしての能力以前に、必要な教養や礼節など、基礎力の形成が追いついていない状況です。
そこで、年間を通じて毎月の例会にて基本に立ち返り、社会的マナーを中心とした研修を実施します。メンバーが青年経済人としての土台を確かなものとし、そのうえで将来的にリーダーとして活躍できる力へと繋げます。
次世代を担うメンバーがリーダーとしての自覚を高め、必要な基礎力を身につけることで、川内青年会議所がまちに必要とされ続ける組織となります。
(会員拡大事業)
「明るい豊かな社会の実現」を目指すためには、持続的に活動できるメンバー体制の構築が欠かせません。組織の活力や事業の質を高めるためにも、新たな人材を迎え入れる取り組みを強化する必要があります。
誰もが会員拡大に取り組みやすい環境を整えるため、実践的なマニュアルの整備やJC運動・活動の魅力を伝えるツールの充実を図ります。さらに、メンバーの経験や想いを共有する機会を設け、「自分もこの活動に加わりたい」と感じられる関わりを生み出し、円滑な拡大活動へと繋げます。
誰もが声を掛け合い、仲間を迎え入れる体制がより整えば、自然と人が集まる魅力的な組織へと成長していきます。その広がりによって、川内青年会議所はまちの未来に貢献し続ける組織となります。
みらい共育委員会 委員長

福留 秀一
現代の子どもは、情報を容易に扱えるようになった一方で、情報を扱う力には個人差があるので安易な情報発信や行動によって、トラブルになる可能性があります。そのため、子どもが情報を見極めて行動できる力を身につける必要があります。
そこで、当委員会では子どもとメンバーが一緒に考えて行動する探究型学習や体験型学習を行います。事業を通して子どもにはすでに有している考えや知識だけが正解ではないことを気づき、他者と交流して得られる情報の重要性を理解していただきます。また、メンバーはこれまでの経験を活かして子どもの前でお手本となる行動を示し、未来のあるべき姿を身近で感じていただきます。
子どもが、情報化社会の中で生き抜く力となる判断力と自主性を習得することで、周囲に流されずに自分の力で行動できる自信を持てるようになります。メンバーと共に成長し続けることでより良い変化が生まれ、持続可能で活気に満ちたまちとなります。
祭 Re:builders委員会 委員長

神 僚宏
従来行われていた地域行事の減少や地域との関係性の希薄化が進み、若者が地域の魅力に触れる機会が限られています。私たちがこれまで培ってきた取り組みや経験を活かし、若い世代とともにまちを支え、未来を共に創っていく姿勢が今求められています。
まちの未来を担う世代とイベント実施に向けた体制を構築し、共にイベントを企画・運営します。また、地域住民や他団体との関係性を深め、柔軟な発想と地域の知見を融合させることで、地域の価値や魅力を再発見し、共に魅力を発信できる機会を創出します。
地域の大人が地域の魅力を伝え続けることで、まちの未来を担う世代がこのまちに温かさを見いだし、これらの取り組みが若者の主体性や郷土愛、当事者意識を醸成します。世代を超えて地域の魅力や価値に触れることで、若者が地元に残りたい、戻ってきたいと想える環境が生まれ、IターンやUターン希望者の増加を生み出し、持続可能なまちづくりへと繋げていきます。
55thanks委員会 委員長

畠中 未来
2026年度、川内青年会議所は創立55周年を迎えました。これまで私たちが運動・活動を展開してこられたのも、先輩方や関係諸団体の皆様のご理解・ご協力の賜物です。60周年に向けて、私たちが先陣を切りこれからの明るい未来を切り拓かなければなりません。
55年の歴史を振り返り、川内青年会議所に関わってこられた全ての方々に感謝の意を伝え、我々が紡いできた伝統やまちづくりへの想いを継承する記念式典を開催します。また、薩摩川内市及びさつま町の社会課題に目を向ける機会を創出することで、私たちの担うべき役割を再確認し、想いを次の世代へ繋ぐ記念事業を開催します。
メンバー一人ひとりが社会課題の本質を捉え、地域を牽引するリーダーとしての自覚を深めることで、より強固な運動・活動を展開してまいります。55年の伝統を次世代への確かな想いへと繋ぎ、誰もが誇れる社会を築きます。

2026年度 出向者紹介
鹿児島ブロック協議会 監査担当役員

池上 亮太郎
2026年度は鹿児島ブロック協議会で監査担当役員という役職をいただき、改めて川内青年会議所の代表として鹿児島県のフィールドへ出向いたします。鹿児島ブロック協議会という組織は日本青年会議所の窓口であり、川内青年会議所と一番近い存在です。LOMとは違った新たな視点の鹿児島ブロック協議会で知識や手法などを学び、持ち帰ることで川内青年会議所の成長の一助となり、薩摩川内市及びさつま町の発展に寄与できればと考えております。
これまでの経験を活かし、川内青年会議所の先輩方が紡いでこられた「川内JCスピリッツ」を現在の鹿児島ブロック協議会でも絶やさぬよう、誇りを持って担いを全うしてまいります。
鹿児島ブロック協議会 運営グループ 財政審査局 局長

中西 諒
この度、鹿児島ブロック協議会財政審査局局長の職をお預かりすることとなりました。通称「財審」と呼ばれるこの機関は、日本本会が策定したコンプライアンスマニュアル、会計マニュアル等の多くのマニュアルに則り、協議会運営のサポートや各委員会が行う運動・活動が鹿児島県内で最大限の効果を発揮することに寄与する機関となります。事業計画を作成し、先導、実行する委員長とは違った立場となりますが、各委員会の展開する事業が鹿児島県内で最大限のインパクトを起こせるようにサポートしてまいります。
私が苦手とする分野ではありますが成長する機会をいただきました。「攻めの財政」「守りの規則」の柱を掲げ一年間走り抜けてまいります。
日本青年会議所 組織グループ JCプログラム推進員会 総括幹事

田中 佑樹
2026年度、日本青年会議所 組織グループ JCプログラム推進委員会の総括幹事として出向させていただきます田中佑樹と申します。LOMと委員会、そして各地会員会議所の架け橋となる役割を全うしたいと考えています。JCプログラムが持つ価値を正しく伝え、誰もが参加しやすく、学びを実践へとつなげられる環境づくりを進めてまいります。また、委員会運営では、円滑な調整や情報共有を徹底し、メンバーが最大限に力を発揮できる体制を整えることを使命とします。「やるかやらないか」ただそれだけ。一人ひとりの成長が組織の力となり、組織の力が地域の未来を拓く。そう信じ、全国の仲間とともに挑戦し続ける一年として邁進してまいります。

概要 / 沿革
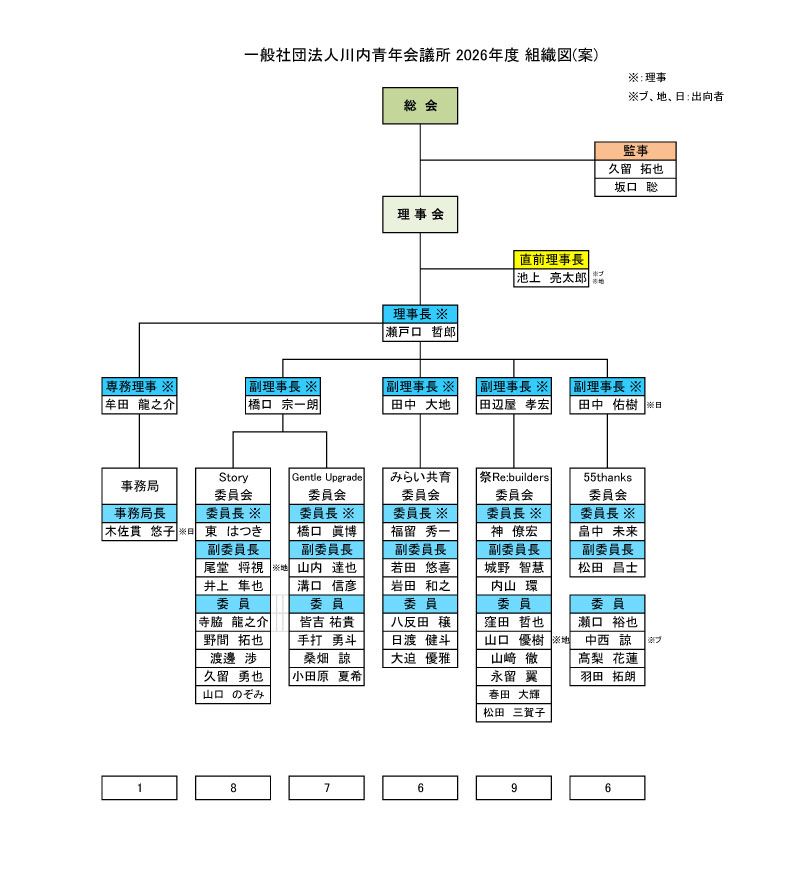
| 創立 | 1972年(昭和47年)2月8日 |
|---|---|
| 社団法人設立 | 1979年(昭和54年)1月1日 |
| 公益社団法人設立 | 2013年(平成25年)1月4日 |
| 日本JC承認番号 | No.496
川内青年会議所の日本JC承認番号がNo496です。新年号はこの496の番号に「簿」をつけて、496簿「よくろぼ」という語呂で作成されています。 |
| 理事長 | 第54代 池上 亮太郎 |
| 川内JCメンバー | 50名(2025年1月現在) |
| 特別会員(OB会員)数 | 154名 |
| 事務局 | 〒895-0052 鹿児島県薩摩川内市神田町3-25 川内商工会議所2F Eメール:info@sendai-jc.org TEL: 0996-22-5938 FAX: 0996-25-3850 |
| 例会場 | 川内商工会議所2F 大ホール |
| 理事会 | 毎月1回 |
| 例会 | 毎月8日 |
定款
| (名称) | ||
|---|---|---|
| 第1条 | 本会議所は、公益社団法人川内青年会議所(英文名Sendai Junior Chamber Inc.)と称する。 | |
| (事務所) | ||
| 第2条 | 本会議所は、主たる事務所を鹿児島県薩摩川内市に置く。 | |
| (目的) | ||
| 第3条 | 本会議所は、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展を図るとともに、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるほか、国内外の関係諸団体との協力を促進し、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。 | |
| (運営原則) | ||
| 第4条 | 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。 | |
| 2 | 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 | |
| (事業) | ||
| 第5条 | 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
|
(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
(2)国政等の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
(3)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(4)前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業
|
||
| 2 | 前項に定めるほか、前項の事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。 | |
|
(1)会員に対し指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
(2)公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所その他の国内及び国外の諸団体との連携、相互理解、親善に関する事業
(3)諸会議・諸大会の開催
(4)その他前各号に定める事業に関連する事業
|
||
| 3 | 前項の事業については、鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺において行うものとする。 | |
| (会員) | ||
|---|---|---|
| 第6条 | 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。 | |
|
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
|
||
| (正会員) | ||
| 第7条 | 鹿児島県薩摩川内市、薩摩郡さつま町及びその周辺に居住し、又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときはその年度内は会員の資格を有するものとする。 | |
| 2 | 他の青年会議所の会員である者は本会議所の会員となることができない。 | |
| (特別会員) | ||
| 第8条 | 満40歳に達した年の事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、理事会の承認を受けて特別会員となることができる。 | |
| (名誉会員) | ||
| 第9条 | 本会議所に功労のあった者で、理事会で承認されたものは、名誉会員となることができる。 | |
| 第10条 | 正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | |
| 2 | 前項の入会申し込みについては、正会員2人以上の推薦のあることを要する。 | |
| (会員の権利) | ||
| 第11条 | 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。 | |
| 2 | 特別会員及び名誉会員は、本会議所の会合に参加することができる。ただし、一切の議決権及び選挙権並びに被選挙権を有せず、かつ、理事会の諮問がある場合に限り、本会議所の運営に関する意見を具申することができる。 | |
| (会員の義務) | ||
| 第12条 | 本会議所の正会員は、本定款に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。 | |
| (入会金及び会費) | ||
| 第13条 | 本会議所の会員(特別会員及び名誉会員を除く。)は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。 | |
| 2 | 入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。 | |
| 第14条 | やむを得ない事由により長期間、本会議所の事業活動に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。休会中の正会員は、書面による委任により議決権及び選挙権、並びに被選挙権を行使することができる。 | |
| 2 | 前項の休会中の会費は、これを免除しない。 | |
| (会員資格の喪失) | ||
| 第15条 | 本会議所の会員は次の事由により、その資格を失う。 | |
|
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(4) 本会議所を解散したとき
(5) 破産手続開始の決定を受けたとき
(6) 第17条の定めにより、除名されたとき
(7) 総正会員の同意があったとき
|
||
| (退 会) | ||
| 第16条 | 正会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、未払いの会費を納入しておかなければならない。 2 退会は、理事長が理事会に報告しなければならない。 3 前2項の規定による正会員の退会は、一般社団・財団法人法上の退社とする。 | |
| (除 名) | ||
| 第17条 | 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総議決権数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。 | |
|
(1) 本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき
(2) 本会議所の秩序を乱す行為をしたとき
(3) 正当な理由がなく会費納入義務を1年以上履行しないとき
(4) 例会又は委員会に対する出席義務を履行しないとき
(5) その他除名すべき正当な事由があるとき
|
||
| 2 | 前項の規定により、会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、総会の日から一週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明の機会を与えなければならない。 | |
| 3 | 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。 | |
| (会員資格喪失に伴う権利及び義務) | ||
| 第18条 | 会員が第15条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 | |
| 2 | 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 | |
| (役員の種類及び定数) | ||
|---|---|---|
| 第19条 | 本会議所に、次の役員を置く。 | |
|
(1) 理事 5名以上24名以内
(2) 監事 2名又は3名 2 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
|
||
| 3 | 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | |
| 4 | 本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事は、この限りではない。 | |
| (理事の任期) | ||
| 第21条 | 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。 | |
| 2 | 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
| 3 | 理事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。 | |
| (監事の任期) | ||
| 第22条 | 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。 ただし、再任を妨げない。 | |
| 2 | 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
| 3 | 監事は、第19条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。 | |
| (役員の解任) | ||
| 第23条 | 理事又は監事が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。 | |
|
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他理事又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき
|
||
| 2 | 理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。 | |
| 3 | 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従いその職務を代行する。 | |
| 4 | 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を総括処理し、理事長又は副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。 | |
| 5 | 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 | |
| (監事の職務権限) | ||
| 第25条 | 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 | |
| 2 | 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。 | |
| 3 | 監事は、総会に出席して意見を述べることができる。 | |
| (監事の理事会への報告義務) | ||
| 第26条 | 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | |
| (監事の理事会への出席義務等) | ||
| 第27条 | 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 | |
| 2 | 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | |
| 3 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 | |
| (監事の総会に対する報告義務) | ||
| 第28条 | 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。 | |
| (監事による理事の行為の差し止め) | ||
| 第29条 | 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 | |
| (責任の免除) | ||
| 第30条 | 本会議所は、理事及び監事の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 | |
| (報酬等) | ||
| 第31条 | 理事及び監事は無報酬とする。 | |
| 2 | 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 | |
| 3 | 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。 | |
| (直前理事長等) | ||
|---|---|---|
| 第32条 | 本会議所に、任意の機関として直前理事長1名を置き、顧問2名以内、相談役2名以内を置くことができる。 | |
| 2 | 直前理事長は、前年度理事長がこれに当たり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 | |
| 3 | 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、その知識及び経験を生かし本会の運営につき適宜助言する。 | |
| 4 | 相談役は、正会員かつ理事長経験者の中から理事長が推薦し、理事会の決議をもって承認とし、理事長の職務の経験を生かし、業務について必要な助言を行う。 | |
| 5 | 直前理事長、顧問及び相談役の任期は、第21条第1項の規定を準用する。 | |
| 6 | 直前理事長、顧問及び相談役の辞任及び解任は、第23条の規定を準用する。 | |
| 7 | 直前理事長、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 | |
| 8 | 直前理事長、顧問及び相談役の報酬は、無報酬とする。 | |
| (特別顧問) | ||
| 第33条 | 本会議所に任意の機関として特別顧問1名を置くことができる。 | |
| 2 | 特別顧問は、理事長が正会員以外から推薦し総会において承認を得るものとする。 | |
| 3 | 特別顧問は、その知識、経験を生かし、本会議所の運営につき適宜助言をする。 | |
| 4 | 特別顧問の任期については、その都度総会において定める。 | |
| 5 | 特別顧問の報酬は、無報酬とする。 | |
| (総会の構成) | ||
|---|---|---|
| 第34条 | 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。 | |
| (総会の種類) | ||
| 第35条 | 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 | |
| (総会の開催) | ||
| 第36条 | 通常総会は、毎年1月に開催し、8月、12月及び必要がある場合に臨時総会を開催する。 | |
| 2 | 1月に開催する通常総会をもって、一般社団・財団法人上の定時社員総会とする。 | |
| 3 | 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 | |
|
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 総議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事にあったとき
|
||
| (総会の招集) | ||
| 第37条 | 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。 | |
| 2 | 理事長は、前条第3項に規定する場合にあっては、遅滞なくその請求又は理事会の議決のあった日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 | |
| 3 | 総会の招集は、少なくとも総会の日の10日前までに正会員に対して、総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。 | |
| 4 | 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。 | |
| (総会の議長) | ||
| 第38条 | 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正会員がこれに当たる。 | |
| (総会の定足数) | ||
| 第39条 | 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 | |
| (総会の決議) | ||
| 第40条 | 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項を除き、出席正会員の有する議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
| (議決権) | ||
| 第41条 | 正会員は、それぞれ各1個の議決権を有する。 | |
| 2 | 総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 | |
| (総会の決議事項) | ||
| 第42条 | 次の事項は、総会の決議を経なければならない。 | |
|
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告(収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表)の承認
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 特別顧問の選任
(6) 入会金及び会費の額の決定及び変更
(7) 会員の除名
(8) 本会議所の解散及び残余財産処分
(9) 会員の資格及び役員の選出に関する規程並びに資金の運用に関する規程の決定、変更及び廃止
(10) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(11) 合併、事業の全部又は一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(12) 公益認定取消しに伴う公益目的取得財産残額の贈与
(13) 理事会において総会に付議した事項
(14) その他、特に重要な事項 2 第36条第3項第2号により、臨時総会を開催したときは、書面に記載した事項以外は、決議することができない。
|
||
| (総会の議事録) | ||
| 第43条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
| 2 | 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。 | |
| 3 | 総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 | |
| (理事会の構成) | ||
|---|---|---|
| 第44条 | 本会議所に理事会を置く。 | |
| 2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 | |
| (理事会の種類) | ||
| 第45条 | 本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。 | |
| (理事会の開催) | ||
| 第46条 | 定例理事会は、毎月1回開催する。 | |
| 2 | 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 | |
|
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 第27条第2項又は第3項、及び第47条第2項又は第3項に定めるとき
|
||
| (理事会の招集) | ||
| 第47条 | 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。 | |
| 2 | 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。 | |
| 3 | 前項の請求があった日から5日以内に、その日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。 | |
| 4 | 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事、各監事、直前理事長、各顧問及び各相談役に対し通知を発しなければならない。 | |
| 5 | 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 | |
| (理事会の議長) | ||
| 第48条 | 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。 | |
| 第49条 | 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が無ければ開会することができない。 | |
| (理事会の議決) | ||
| 第50条 | 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | |
| (理事会の権限) | ||
| 第51条 | 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。 | |
|
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職。ただし、理事長の選定に当たっては、総会の決議により別に定める役員選任規程により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる 。
(6) 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画等」という。)の承認
(7) 前各号に定めるもののほか、本会議所の業務執行の決定
|
||
| 2 | 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。 | |
|
(1) 重要な財産の処分及び譲受
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人(事務局員等)の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6) 第30条の責任の免除 (報告の省略)
|
||
| (報告の省略) | ||
| 第52条 | 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 | |
| 2 | 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告には適用しない。 | |
| (議事録) | ||
| 第53条 | 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。 | |
| (例 会) | ||
|---|---|---|
| 第54条 | 本会議所は、毎月1回以上例会を開く。ただし、総会の開催される月は、その限りではない。 | |
| 2 | 例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。 | |
| 3 | 正会員は、例会への出席義務を負う。 | |
| 4 | 例会は何らの議決権を有さないものとする。 | |
| (委員会の設置) | ||
| 第55条 | 本会議所は、その目的を達成するために委員会を置く。 | |
| (委員の任命) | ||
| 第56条 | 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。 | |
| 2 | 委員長は、理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを任命し、副委員長及び委員は、正会員の中から委員長が理事会の承認を得て任命する。 | |
| 3 | 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、全員いずれかの委員会等、事務局に所属するものとする。 | |
| 4 | 正会員は、委員会への出席義務を負う。 | |
| (事業年度) | ||
|---|---|---|
| 第57条 | 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 | |
| (資産の構成) | ||
| 第58条 | 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 | |
|
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
|
||
| (経費の支弁等) | ||
| 第59条 | 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。 | |
| (事業計画及び収支予算) | ||
| 第60条 | 本会議所の事業計画、収支予算及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し理事会の承認を得た後、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 | |
| 2 | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |
| (事業報告及び決算) | ||
| 第61条 | 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第2号の書類についてはその内容を報告し、第1号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 | |
|
事業報告
事業報告の附属明細書
計算書類及びその付属明細書並びに財産目録
|
||
| 2 | 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 | |
|
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
|
||
| (公益目的取得財産残額の算定) | ||
| 第62条 | 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条2項第4号の書類に記載するものとする。 | |
| (資産の団体性) | ||
| 第63条 | 本会議所の会員は、その資格を喪失した場合において、本会議所の資産に対し、いかなる請求もすることができない。 | |
| (会計原則) | ||
| 第64条 | 本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。 | |
| (情報の公開) | ||
|---|---|---|
| 第65条 | 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 | |
| 2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
| (個人情報の保護) | ||
| 第66条 | 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 | |
| 2 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
| (公 告) | ||
| 第67条 | 本会議所の公告は、電子公告による。 | |
| 2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
| (個人情報の保護) | ||
| 第66条 | 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 | |
| 2 | 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
| (公 告) | ||
| 第67条 | 本会議所の公告は、電子公告による。 | |
| 2 | その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
| (定款の変更) | ||
|---|---|---|
| 第68条 | この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。 | |
| (合併等) | ||
| 第69条 | 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 | |
| (解 散) | ||
| 第70条 | 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。 | |
| (清算人) | ||
| 第71条 | 前条の事由によって解散する場合、清算人は、その総会においてこれを選任する。 | |
| 2 | 清算人は、就任の日より清算事務を行い、総会の決議を得て残余財産についての処分の方法を定めなければならない。 | |
| (解散後の会費) | ||
| 第72条 | 本会議所は、解散後であっても総会の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。 | |
| (残余財産の処分) | ||
| 第73条 | 本会議所が清算するときに存する残余財産は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。 | |
| (公益目的取得財産残額の贈与) | ||
| 第74条 | 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 | |
| (事務局) | ||
|---|---|---|
| 第75条 | 本会議所は、その事務を処理するため、事務局を設置する。 | |
| 2 | 事務局には、事務局長1名、財政局長1名、その他必要な職員を置くことができる。 | |
| 3 | 事務局長は、理事長の命を受け事務局を統括する。 | |
| 4 | 財政局長は、理事長の命を受け、事務局の財務全般を統括する。 | |
| 5 | 事務局長及び財政局長は、役員を除く正会員の中から、理事会で選任する。 | |
| 6 | 前各号に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は理事会において別に定める。 | |
| (委 任) | ||
|---|---|---|
| 第76条 | 本定款に別に定めがあるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により定める。 | |
| 1, | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
|---|---|
| 2, | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第57条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
| 3, | 本会議所の最初の理事長は中間則行、副理事長は上原亮祐、森山博信、手打哲也、専務理事は内田一樹とする。 |
イメージキャラクター
- 日本では数少ない地域でしか発見されていない甑島のティラノサウルス
- 日本一の川内大綱引
- シェア全国No.1を誇る川内名産の甲冑
- さつま町の名産である竹
名称について

